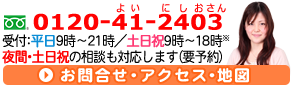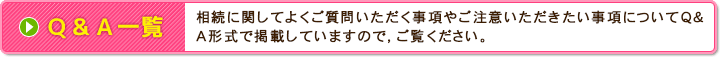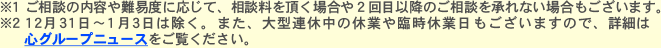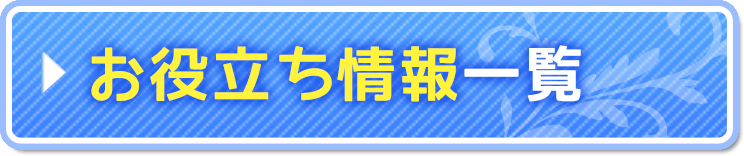遺言の方式
1 遺言の方式とは
遺言は、民法の定める方式に従わなければ、無効とされてしまいます。
遺言者の相続開始後に効力が発生するものであるため、遺言者の遺言時の真意がどのようなものであったのかについて、相続開始後に紛争が生じるおそれがあります。
そこで、遺言者の真意を厳格にチェックするために、遺言者は一定の方式に従って遺言を行わなければならないとされているのです。
民法は、自筆証書遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言などの個別の方式を定め、さらに、これらに共通する事項として、加除変更の方式などを定めています。
実際には、遺言の方式の一部を守っていない遺言についても、裁判所が有効であるとした事案もありますが、これらの事案はあくまでも例外的な救済が認められたものに過ぎません。
ですから、相続開始後に遺言が無効とされないよう、遺言作成段階では、厳格に民法の定める方式を遵守していく必要があるといえます。
このため、遺言を作成するにあたっては、自筆証書遺言である場合を含め、一度は相続問題に詳しい弁護士などのチェックを受けておいた方がよいかと思います。
2 共同遺言の禁止
2人以上の者が同一の証書で遺言することを、共同遺言といいます。
民法上、共同遺言はできないものとされており、相続開始後も共同遺言は無効と扱われます。
ただし、判例には、作成名義の異なる2通の遺言書が別紙に記載され、それらが1つにつづり合わされていた(容易に切り離すことが可能)遺言について、両者に内容上の関連性もないことも考慮し、例外的に共同遺言に当たらないとしたものがあります(最判平成5年10月19日家月46巻4号27頁)。
共同遺言の禁止でしばしば問題となるのは、夫婦間で次のような内容の遺言が行われる場合です。
「夫が先に亡くなったら、妻に、夫の持っている一切の財産を相続させる。妻が先に亡くなったら、夫に、妻の持っている一切の財産を相続させる。」
現実に、夫婦でお互いが亡くなった後のことを慮り、このような内容の遺言を行いたいと希望することがしばしばあります。
しかし、このような遺言が同一の遺言書で行われた場合は、同一の証書で2人が遺言を行ったことになりますので、共同遺言の禁止の原則により、遺言が無効とされてしまいます。
判例も、例え、一方が自書していなかった(遺言の方式違反がある)場合でも、両方の遺言が無効になるとしています(最判昭和56年9月11日判時1023号48頁)。
このような内容の遺言を行いたい場合は、夫が「遺言者○○は、その妻××に、一切の財産を相続させる」という内容の遺言を、妻が「遺言者××は、その夫○○に、一切の財産を相続させる」という内容の遺言を別々の証書において行う必要があります。
なお、このような遺言を行った場合は、相続開始後、他の相続人が遺留分侵害額請求権を行使する可能性があるため、注意しなければなりません。
3 遺言書の加除変更
遺言書を作成する際には、誤記を訂正する必要が出てきたり、後で遺言に変更を加えたくなったりすることがあります。
このような場合には、被相続人自らの手で、遺言書に加除変更を行う必要があります。
民法は、遺言書(公正証書遺言を除く)に加除変更を行う場合には、加除変更したことを付記して署名した上で、加除変更した場所に押印しなければならないとし、厳格な方式を定めています。
具体的には、①加除訂正を行った場所に押印した上で、左部欄外に、「この行1字訂正」と記載し、そこに署名するか、②加除訂正を行った場所に押印した上で、遺言書末尾に、「この遺言書5行目中「○○」とあるのを「××」と訂正した。」と記載し、そこに署名する必要があります。
このような方式に違反した加除変更は無効です。
さらに、場合によっては、加除変更の方式違反により、相続開始後に、遺言書全体が無効とされることもあります。
日付の変更につき、抹消部分が判読できないため、遺言書全体が無効とされた例があります(仙台地判昭和50年2月27日)。
とはいえ、加除変更部分がわずかで、かつ付随的なものであり、その部分を除外しても遺言の主要な趣旨が表現されている場合には、遺言全体の効力には影響しないとされた例もあります(大阪高判昭和44年11月17日)。
最高裁も、明らかな誤記の訂正については、方式違反があっても、遺言全体が無効となるものではないとしています(最判昭和56年12月18日民集35巻9号1337頁)。
参考リンク:最高裁判所判例集
いずれにしても、相続開始後に被相続人の意思を確実に実現するためには、民法の方式を厳格に守った方がよいと思います。
方式の確認に当たっては、弁護士などの相続の専門家のチェックを受けるのがおすすめです。