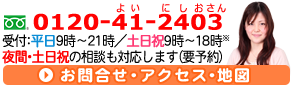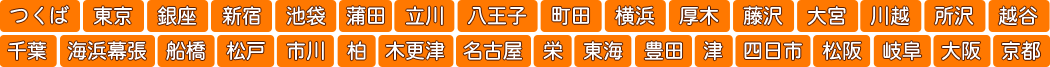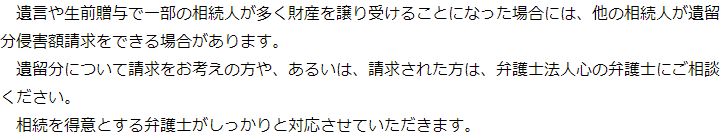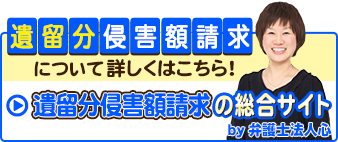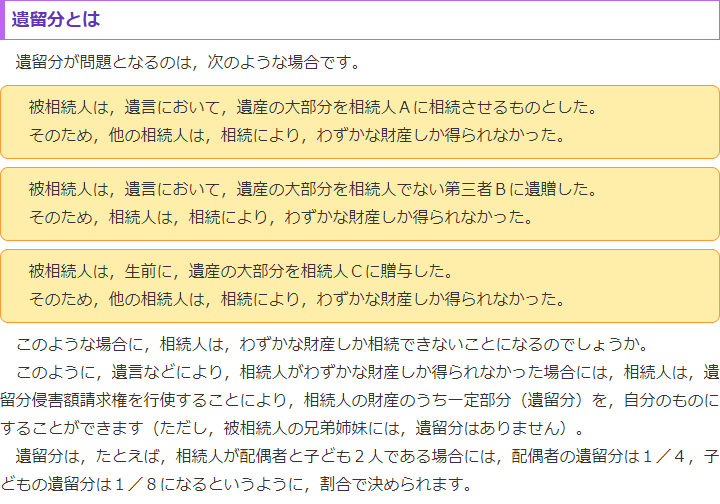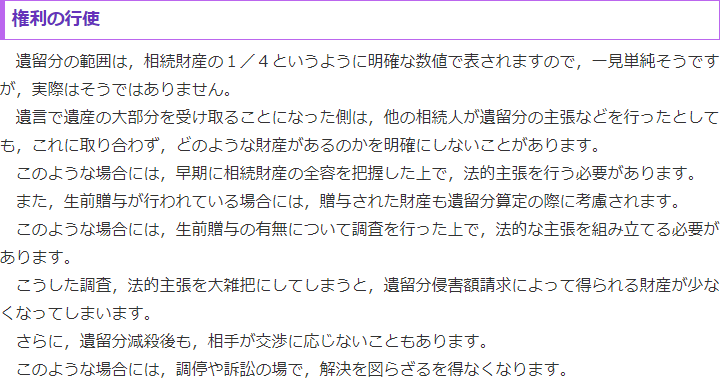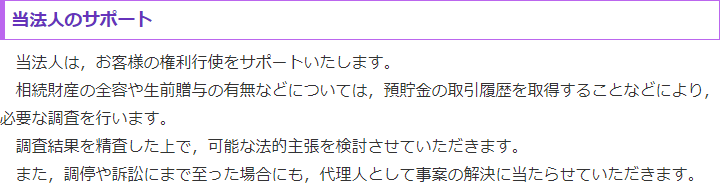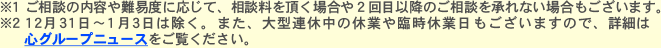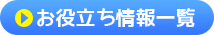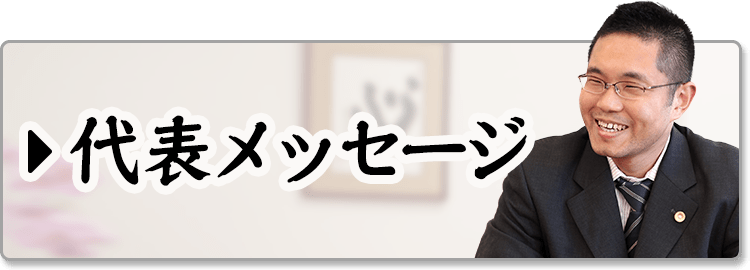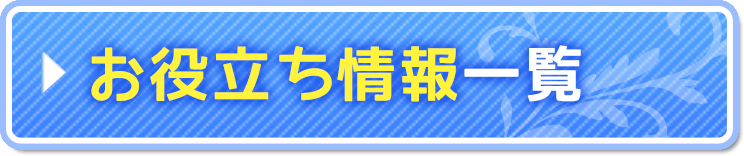遺留分侵害額請求
-
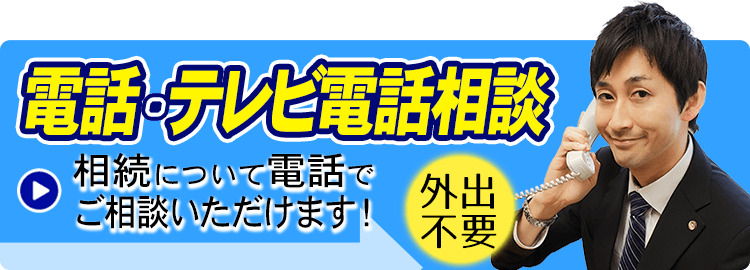
電話・テレビ電話相談の実施
来所が難しい場合でも電話・テレビ電話相談ができますので、より気軽に相談をしていただけます。
-

遺留分のお悩みについて
相続分野を集中的に扱い、遺留分を得意とする弁護士が対応いたします。
東京駅近くで相談ができます
東京駅近くに事務所があり、周辺にお住まいの方やお勤めの方にとって利用していただきやすい環境となっています。所在地等の詳細はこちらをご確認ください。
遺留分権利者の範囲
1 原則は「兄弟姉妹以外の相続人」

法律上、遺留分は、「兄弟姉妹以外の相続人」に対して認められると定められています(民法1042条1項)。
つまり、被相続人の配偶者や子は、基本的に相続人となるので(民法887条1項、890条)、原則として遺留分権利者となります。
また、被相続人の両親等の直系尊属は、子やその代襲者である孫が相続人とならない場合には相続人となるため(民法889条1項1号)、その場合には、当該直系尊属に当たる方も遺留分権利者となります。
なお、被相続人に子供がおり、直系尊属が相続人とならない場合には、当該直系尊属の方は遺留分権利者とならないので、ご注意ください。
2 代襲相続人も遺留分権利者となる
相続人となるべき子がすでに亡くなっている場合や、相続欠格(民法891条)や相続排除(民法892条)によって相続人とならない場合には、被相続人の孫が代襲相続によって相続人となることがあります(民法887条2項)。
このような場合、相続人である孫は「兄弟姉妹以外の相続人」に当たるので、遺留分権利者となります。
再代襲相続によって、被相続人のひ孫が相続人となった場合も同様に、相続人である当該ひ孫は「兄弟姉妹以外の相続人」に当たるため、遺留分権利者となります。
3 兄弟姉妹には遺留分が認められていない
上記のように、法律上「兄弟姉妹以外の相続人」に遺留分が認められると定められています。
つまり、被相続人に子や両親がおらず、被相続人の兄弟姉妹が相続人になったとしても、被相続人の兄弟姉妹の方には遺留分が認められません。
そのため、兄弟姉妹に当たる方は、被相続人の遺言の記載等によって、少ない財産しか得られなかったとしても、遺留分侵害額請求権を行使できないため、ご注意ください。
4 遺留分侵害額請求権の譲渡・相続
相続発生前、すなわち被相続人が亡くなる前は、遺留分侵害額請求権を譲渡することは認められないと考えられています。
しかし、被相続人が亡くなり、相続が開始した後は、遺留分侵害額請求権の譲渡をすることが認められるケースがあります。
この場合には、相続人等から遺留分侵害額請求権の譲渡を受けた人が、当該請求権を行使することになります。
また、遺留分侵害額請求権を有する方が亡くなった場合、遺留分侵害額請求権も相続の対象となるため、遺留分権利者の相続人等に承継されることがあります。
このような場合には、遺留分侵害額請求権を行使できる人は誰なのかという問題は、どんどん複雑になっていってしまいます。
5 遺留分権利者について疑問に思ったら
相続に際して、自分は遺留分権利者に当たるのではないか、または、相手から遺留分侵害額請求権を主張されたが、相手は本当に遺留分権利者に当たるのか等の疑問が生じる場合もあるかと思います。
場合によっては、遺留分権利者に当たるか否かの判断が容易ではないこともあります。
そのような場合には、弁護士にご相談ください。
遺留分を請求する方法
1 内容証明郵便を使って請求を行うことが多い

遺言書や生前贈与で多額の財産を受け取っている相続人がいて、遺留分が侵害されている場合、他の相続人は、遺留分侵害額請求を行って金銭の支払いを求めることができます。
遺留分侵害額請求をするにあたって、「このように請求しなければいけない」という法律はありません。
そのため、法律面だけをみれば、書面で請求する必要もなく、裁判をする必要もないですし、それこそ、口頭で請求してもよいということになります。
しかし、実際には、まず内容証明郵便を使って請求をするケースが多いです。
内容証明郵便は、送った手紙の内容について郵便局が控えを取り、誰に何をいつ送ったかを証明してくれるサービスです。
郵便サービスの一つで、法律上の請求では頻繁に使われています。
2 請求時に内容証明郵便を使う理由
⑴ 1年の時効
なぜ内容証明郵便を使うのかというと、遺留分侵害額請求には時効があり、時効が成立する前に請求をしたという証拠を残しておくためです。
遺留分侵害額請求は、
・相続の開始
・贈与又は遺贈があったこと
を知ったときから、1年以内にしなければ、請求ができなくなってしまいます。
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
民法1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。
つまり、一例として、亡くなったこと(相続の開始)か、遺言書があったこと贈与又は遺贈があったことのどちらか一方を知らなければ大丈夫なのですが、両方知ってしまうと1年の時効がスタートしてしまいます。
一方で、1年以内に1回でも遺留分侵害額請求をしておけば時効はストップし、次の時効は5年になります。
⑵ 内容証明郵便を使うメリット
日常生活などで使う書留郵便等は、「“〇月〇日”に“○○さん”に手紙を送った」ことの証明には役立ちます。
しかし、時効をストップするために重要なことは、「“〇月〇日”に“○○さん”に“遺留分侵害額請求をしたこと”」を証明する、つまり、手紙の内容が重要です。
書留郵便等では、封筒の中身については証明をしてくれないため、例えば、裁判で「届いた封筒は空だったため、遺留分侵害額請求はされていない」と主張されてしまう可能性もあるわけです。
そこで、送った内容まで証明してくれる内容証明郵便で遺留分侵害額請求を行い、確実に時効をストップする必要があります。
3 内容証明郵便を受け取ってもらえない場合
内容証明郵便を送ったとしても、相手に到達しないと時効はストップしません(民法97条1項)。
例えば、1年ギリギリで内容証明郵便を送ったところ、相手が不在で届かなかったときは、時効はストップしません(※)。
民法97条(意思表示の効力の発生時期等)
1 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
こういった場合は、
・裁判を起こす
・相手のポストに直接投函をして、その様子を記録に残す
など、特殊な対応が必要になります。
※ なお、相手が、居留守を繰り返すなど、正当な理由なく受け取らないときは、受け取り拒否をしたときに時効はストップします(民法97条2項)。
4 家庭裁判所における調停
内容証明郵便を送った後は、まず当人同士で話合いになるわけですが、相手が遺留分を認めなかったり、金額の折り合いがつかなかったり等で、話合いがまとまらないことはあります。
話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を提起することになります。
調停とは、訴訟とは異なるもので、裁判所における話合いです。
当事者が家庭裁判所に出廷し、調停員を介して話合いをします。
具体的には、遺留分を請求する側と遺留分を請求される側が調停員のいる部屋に交互に入り、それぞれの言い分を調停員に伝え、裁判官の意見を聞きながら双方が納得できる解決を模索します。
合意ができると、裁判所で調停調書という書類が作成され、解決となります。
5 調停がまとまらない場合は、地方裁判所で訴訟
家庭裁判所における調停では、あくまで双方が合意をしないと、調停調書は作成できません。
そのため、調停で解決しないこともあります。
この場合は、地方裁判所に訴訟を起こすことになります。
訴訟であれば、最終的には、裁判所が判決を出すことになるため、当事者が納得をするかどうかにかかわらず結論が出ることになります。
6 遺留分の請求をお考えの方は、まずは弁護士に相談を
今までの説明でお分かりいただけたかと思いますが、遺留分侵害額請求は、時効の問題もあり、請求を行う時点から慎重に進めていくべきです。
請求時の手紙の内容が時効の問題をクリアできる内容になっているか、金額交渉をどうするか、調停・訴訟など、裁判所を利用するかなど、専門的な判断が求められます。
遺留分の請求をお考えの方は、まずは弁護士にご相談ください。
遺留分を請求したい方へ
1 遺留分侵害額請求はまずご相談を

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められた最低限の相続をする権利のことです。
遺留分は、相続人が配偶者や子の場合は相続分の2分の1、直系尊属の場合には相続分の3分の1と法律で決められています。
遺言書などによって特定の人が遺産を多く取得するなどの場合には、他の相続人の遺留分が侵害されているおそれがあり、遺留分侵害額請求によって遺産を取り戻すことができる可能性があります。
遺留分侵害額請求の対象となる遺産の範囲や評価額などについて、例えばどこまでの生前贈与が対象となるか、不動産の評価額はいくらか等、争いになることが多いです。
また、遺留分侵害額請求の時効は、請求ができる時から1年間と短く設定されているため、早急に遺留分侵害額請求の意思を、内容証明郵便などの証拠として残る形で相手方に伝える必要があります。
相手方が内容証明郵便を受け取らない場合等は、訴訟提起を急がなければならないケースもありますので、できるだけ早く相談することをおすすめします。
また、遺留分侵害額請求をして受け取った金額については、相続税がかかる場合がありますので、その際は、税理士への相談が必要になる可能性もあります。
2 相続法改正も踏まえた上で対応することの重要性
令和元年7月の相続法改正により、遺留分につき2つの大きな変更がありました。
1つ目は、生前贈与に対する遺留分請求の期間制限です。
これまでは生前贈与に対する遺留分侵害額の請求に、期間制限はありませんでしたが、改正により亡くなる前10年間に限定されています。
請求できるかできないかにつき、以前よりも判断が厳しくなっています。
2つ目は、遺留分請求権が金銭債権に変わったということです。
実質的に大きな変更点ではないように思えますが、被相続人の財産調査をする際に、これまでは遺言により財産を相続しない相続人も遺留分権利者であることで預金債権者となっていましたが、単なる金銭債権に変更されたことで預金債権者ではなくなったことを理由に、資料開示を拒む銀行も出てきています。
このような法改正を踏まえた上で遺留分侵害額請求を進めるためには、やはり弁護士にご依頼いただくことが重要かと思われます。
3 遺留分のご相談をお待ちしています
遺留分侵害額請求については、できるだけお早めに相談されることをおすすめします。
私たちは、弁護士や税理士などの複数の専門家が協力して、相続のお悩みをトータルサポートできるよう努めておりますので、遺留分についてお悩みのことがあればどうぞご相談ください。