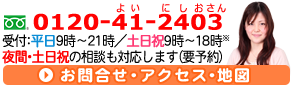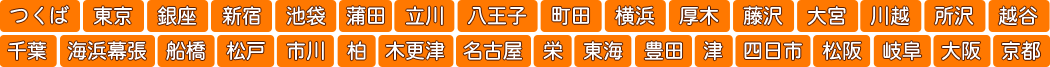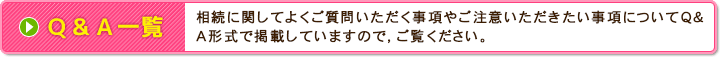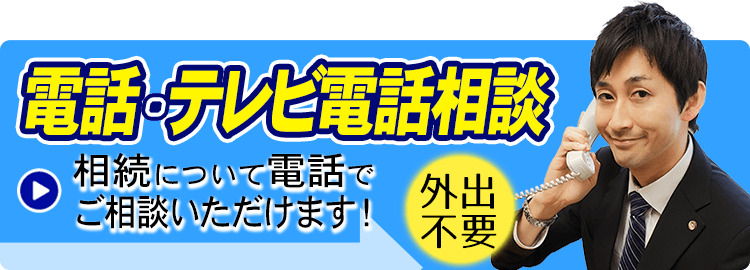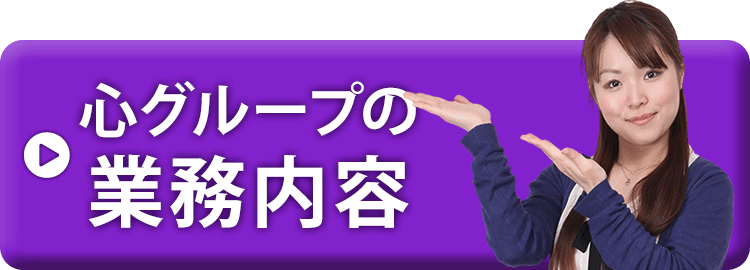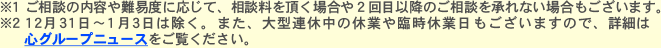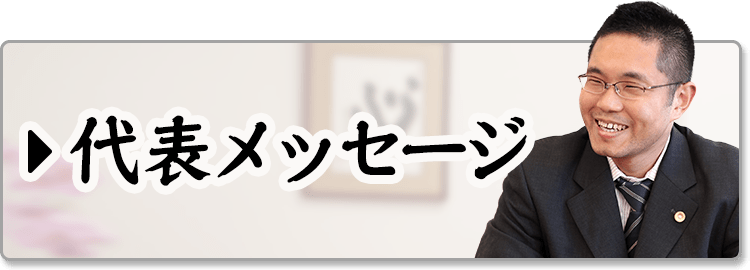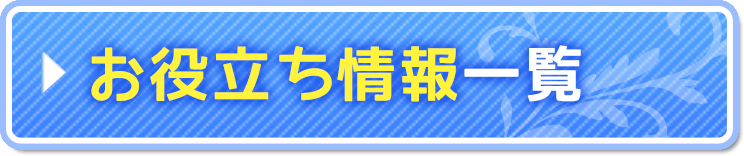二次相続を見据えた相続税対策
1 二次相続とは
二次相続とは、例えば父と母と子の3人家族でいうと、父が最初に亡くなって、父の遺産を母と子が相続(一次相続)した後に、母が亡くなって母の遺産を子が相続するという場合、二回目の相続のことをいいます。
このような二次相続が発生するケースにおいては、特に相続税の申告・納付の場面で、問題が起こり得る場合があります。
具体的には、一次相続において納税額が少なくなることのみ考えて相続をすると、二次相続まで含めたトータルの納税額において、結果的に納税額が多額になってしまうというような事態が起こり得ます。
そこで、二次相続まで見据えた相続税対策が必要になります。
2 配偶者の税額軽減の制度を一次相続で利用する場合の注意点
⑴ 一次相続で税額が安くなっても二次相続で高額になる場合がある
父が死亡して一次相続が発生する場合、配偶者である母は、相続税の申告の際に配偶者の税額軽減の制度を活用すると考えられます。
配偶者の税額軽減の制度を利用すると、配偶者については、相続税の課税価格が法定相続分を下回る場合には相続税は課税されず、また、課税価格が法定相続分を上回る場合でも、その額が1億6000万円以下の場合には相続税が課税されないことになります。
参考リンク:国税庁・配偶者の税額軽減
そのため、配偶者である母が遺産を多めに取得するようにしておけば、一次相続での税額を少なくすることができます。
しかし、その次の二次相続では、この配偶者の税額軽減の制度を利用することはできません。
さらに二次相続の場合、父から母へ受け継がれた財産に加え、もともと母の持っていた財産を、相続人である子一人が相続することになり、相続する遺産の額が増えますので、その分相続税も増加してしまうことがあります。
このように、一次相続において配偶者の税額軽減制度を最大限に活用して相続税を少なくしたとしても、二次相続で多額の相続税を納付することになってしまうと、結果として節税の効果が発揮されないことになってしまうのです。
⑵ 二次相続で多額の相続税が発生する要因
このような事態が生じる要因としては、相続税の申告における基礎控除の額が、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」という算定によって決まることが挙げられます。
二次相続においては、法定相続人の人数が減るため基礎控除の額も減り、納める相続税額が高くなってしまいます。
他にも、一次相続から二次相続までの間に財産の価値が上昇してしまい、結果として課税価格が高くなってしまうこと等が挙げられます。
したがって、一次相続の段階から二次相続での相続税も考慮しておくことが大切です。
他の特例の適用も考慮に入れて、二次相続が発生した場合を想定した納税額の試算を何通りかしてみたり、将来値上がりが予想される財産は一次相続の段階で子が取得したりするといった対策をすることが必要となります。
このような二次相続まで見据えた相続税対策については、税理士にご相談ください。
相続した土地や建物などの名義変更をしないとどうなるのか 相続税の課税対象となる財産とは