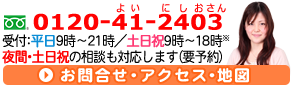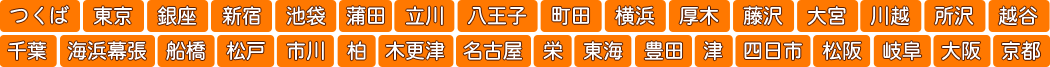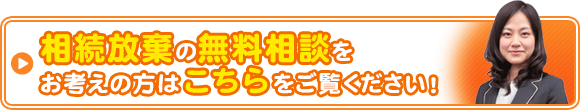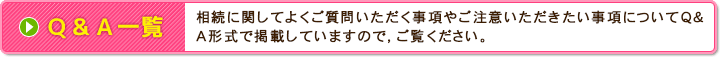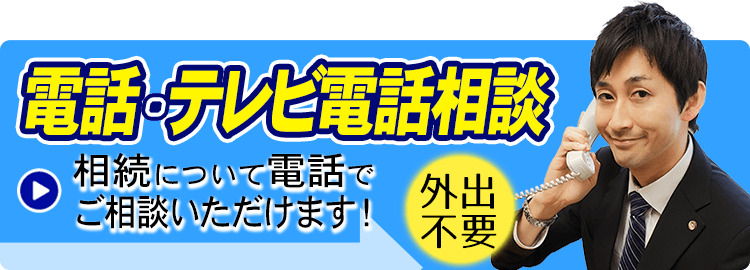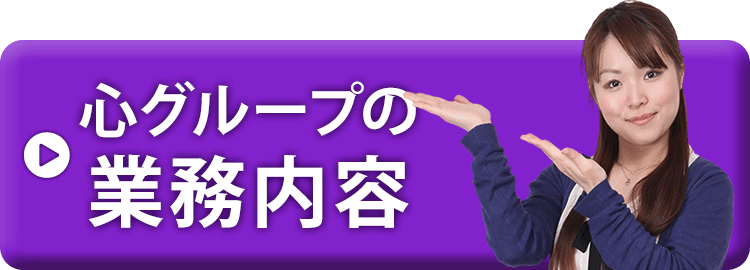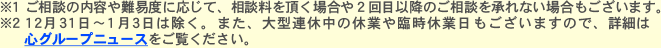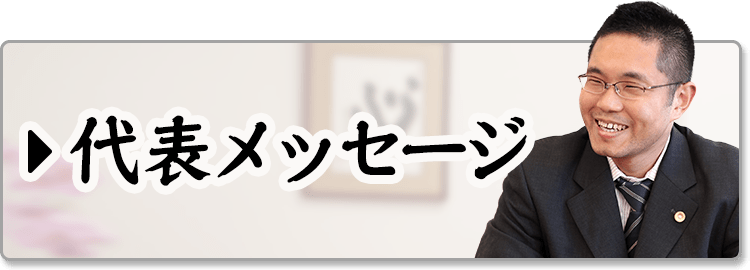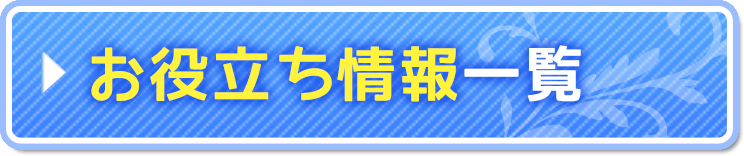相続放棄の熟慮期間
1 相続放棄は3か月以内に行わなければならない
相続放棄の熟慮期間は、相続放棄をするかあるいは相続をするかについて検討するための期間であり、この期間は、「相続の開始があったことを知った時」から3か月以内です。
相続発生後、相続人は、家庭裁判所に申し立てることにより、相続放棄をすることができます。
参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述
相続放棄が認められると、はじめから相続人ではなかったことになります。
そのため、例えば亡くなった人に借金があった場合に、その借金を一切支払わなくてよくなるというとても強力な効果が発生します。
2 熟慮期間のスタートは「相続の開始があったことを知った時」
相続放棄の熟慮期間のスタートは、「相続の開始があったことを知った時」です。
一般的には、親など近しい人が亡くなった場合には、その当日に亡くなったことを知るため、
「相続の開始があったことを知った時」=死亡日
となることが多いです。
もっとも、厳密には、この「相続の開始があったことを知った時」とは、
① 相続の開始があったこと
例1)親が死亡して、子供が相続人になった。
例2)実の子である相続人が相続放棄をし、亡くなった人の兄弟である自分に相続の権利が回ってきた。
② ①を知ったこと
例1)死亡したことを知った。
例2)実の子である相続人が相続放棄をしたことを知った。
の2つの条件を満たす必要があります。
そのため、
「相続の開始があったことを知った時」≠死亡日
となるケースも珍しくありません。
3 「相続の開始があったことを知った時」が死亡日と一致しないケース
⑴ 独居していた叔父が亡くなったことを警察から教えられたケース
亡くなった人に子供がいない場合、その兄弟や甥姪が相続人になることがあります。
そのため、一度、親戚の集まりで会っただけの人から相続をするというケースも考えられます。
ただでさえ疎遠な上、その人が独居しており、孤独死をしてしまうと、発見が遅れてしまうこともあり得ます。
死亡後、しばらく経ってから通報などにより警察が発見し、その後警察から親戚に連絡が来ることもあります。
この場合は、
「相続の開始があったことを知った時」=警察からの連絡があった日
となります。
⑵ 実の子供が相続放棄をしたケース
相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになります。
そのため、実の子供が相続放棄をしたケースでは、子供がいない場合の相続と同じく、死亡した人の兄弟や甥姪が相続人となる場合があります。
この場合、死亡したことは当日に知っていたとしても、その時点では、まだ死亡した人の子供が相続人であるため、死亡した人の兄弟は相続人ではありません。
そのため、この時点ではまだ、「相続の開始」とはなりません。
「相続の開始」は、実の子供が相続放棄をした時点になります。
このようなケースの場合は、
「相続の開始があったことを知った時」=死亡した人の子供が相続放棄をしたことを知った時
になります。
4 相続放棄のご相談はお早めに
亡くなった方に借金などの債務があった場合、相続放棄が認められないと、その借金を受け継ぐことになり、多大な不利益を負ってしまいます。
上記3のようなケースで、思いもよらず相続人となる場合もあり得ます。
疎遠な親戚の相続人となった場合、亡くなった方にどれくらいの財産があり、債務があるのかといったことがよく分からないケースも多いです。
上記の熟慮期間内に財産や債務を調査し、しっかりと検討の上で、相続放棄をする場合には期限に間に合うよう手続きを進めることになります。
3か月という期間は思いのほかあっという間に過ぎてしまいますので、相続放棄を検討されている場合、まずはお早めにご相談ください。