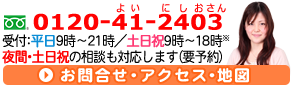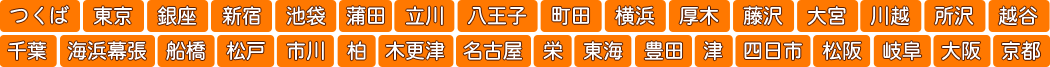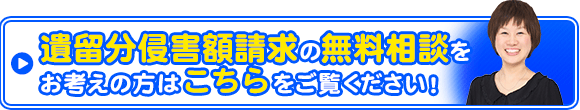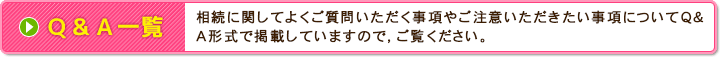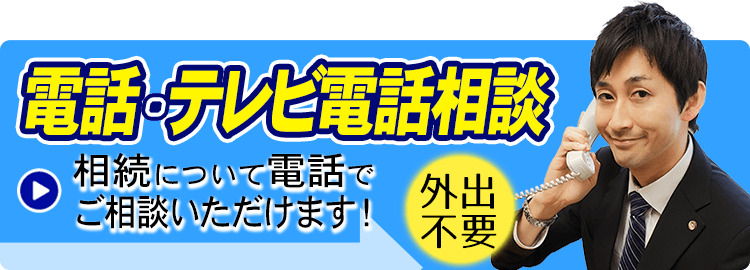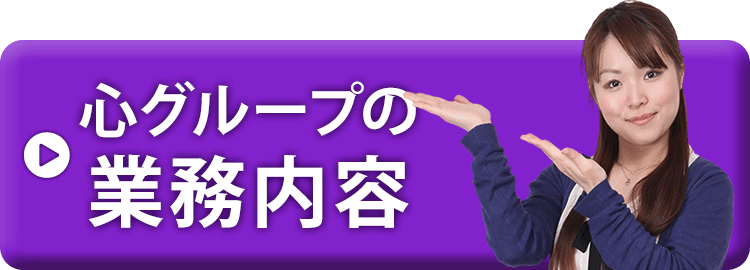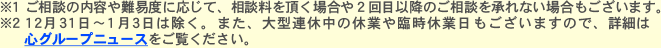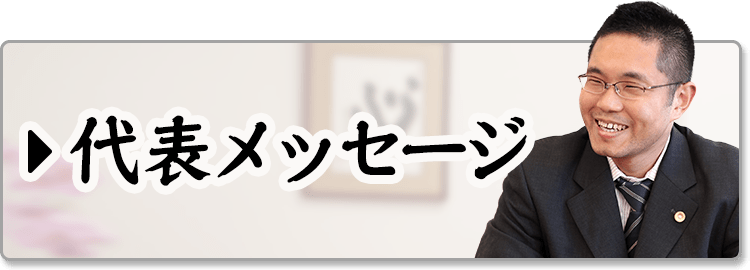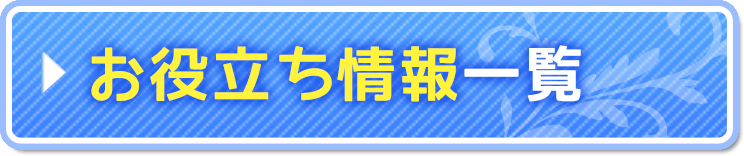遺留分対策について
1 遺留分対策を考えるにあたって
遺言によって自身の希望に沿った相続ができるとはいえ、遺言をもってしても遺留分を完全に奪うということはできません。
遺留分権利者の遺留分を侵害するような遺言の内容にしてしまうと、相続後にトラブルとなり、遺留分侵害額請求をされてしまうおそれがあります。
そのため、遺言を残す際に遺留分が原因となって、自分の望む相続ができなくなってしまうことを心配されている方もいらっしゃるかと思います。
そもそも遺留分は、一部の相続人に認められた最低限の財産を取得する権利です。
遺留分を完全に奪うという発想で遺言を作成してしまうと、その遺留分をめぐってトラブルが発生したり、後から裁判所に遺言の有効性を否定されたりするリスクが大きくなってしまいます。
近年、遺留分対策の家族信託が無効と判断された裁判例があることは記憶に新しく、遺留分対策というのは、様々な角度から少しずつ、遺留分制度の根幹を害しない合理的な範囲で検討をしていくべき事項といえます。
2 具体的な遺留分対策
⑴ 遺留分の対象となる遺産を減らす
まずは、遺留分の対象となる遺産を減らすという考え方があります。
例えば、現金ではなく生命保険という形で財産を残す方法が挙げられます。
死亡保険金は生命保険契約に基づく金員です。
保険金を受け取る人の財産と考えられるため、原則として遺留分の対象とはなりません。
ただし、遺留分制度の趣旨に照らし合わせて考えたときに、遺産の額と比べてあまりに不合理なほど生命保険の額が多い場合には、死亡保険金に対しても遺留分請求が認められるという判例があります。
また、令和元年の相続法改正により、生前贈与に対する遺留分請求権は原則として生前10年前までに限る旨の限定がされましたので、いわゆる暦年贈与を利用した対策が、相続法改正前よりも有効になっています。
⑵ 遺留分の対象となる遺産の評価額を下げる
次に、遺留分の対象となる遺産の評価額を下げるという考え方があります。
預貯金を不動産に変えるというのが中心ですが、自社株の場合に会社の評価額を下げるという対策も含みます。
ただ、評価額については、紛争になったときに、当然ながら複数の評価方法がありますので、効果については流動的です。
3 遺留分対策でお悩みの方はご相談ください
相続対策を考える上では、法律の知識だけではなく、税金や不動産など様々な分野の知識が必要になってきます。
私たちは、お客様の様々な相続のお悩みを解決すべく、弁護士法人心の弁護士や税理士法人心の税理士など、各専門家がお互いに協力し合える体制を整えております。
それぞれ、相続を集中して扱い、得意とする者が対応させていただきます。
また、相続分野においては法改正も頻繁に行われておりますので、定期的な研修により、各制度や法改正をはじめ、税法など、相続に関する知見を深めたり、最新の裁判例を共有したりするなど、日々研鑽を積んでいます。
東京駅から徒歩3分、地下鉄日本橋駅から徒歩2分のところに事務所がありますので、東京で遺留分対策をお考えの方はお気軽にご相談ください。
遺産分割協議で相続人が全員そろわない場合の対処法 相続放棄の熟慮期間