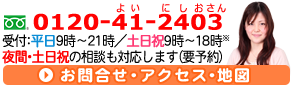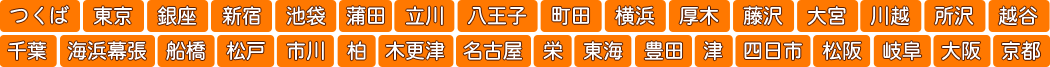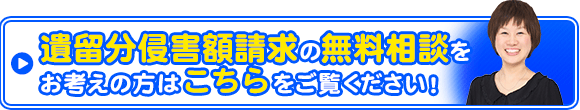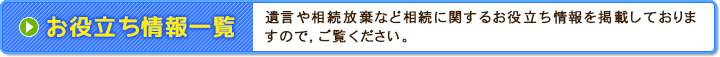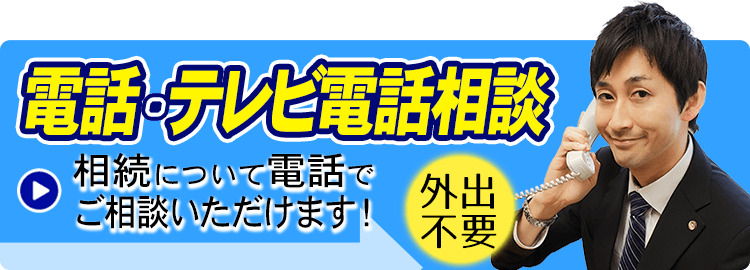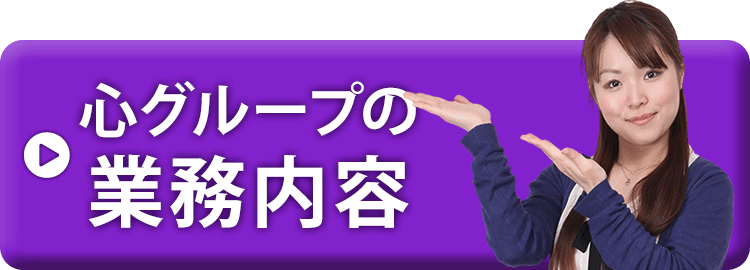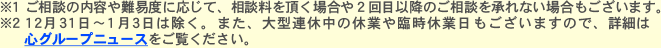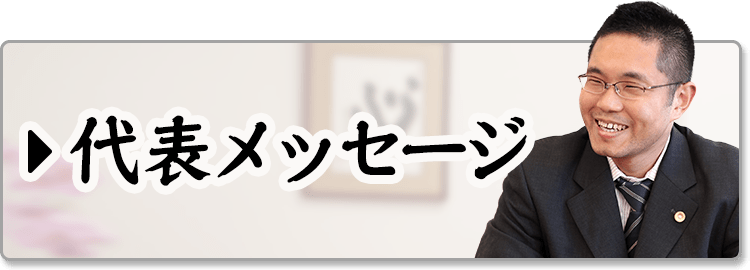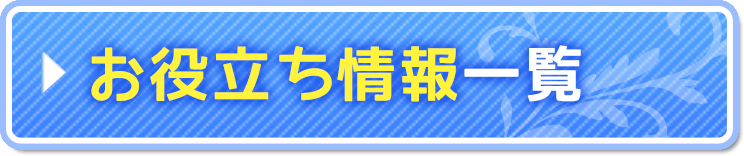遺留分の時効に関するQ&A
遺留分侵害額請求をするのに期限はありますか?
はい、遺留分侵害額請求権には時効があります。
民法には、「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅する」とあります(民法第1048条前段)。
また、相続開始の時から10年を経過したときも権利を行使することができなくなります(民法第1048条後段 いわゆる除籍期間)。
さらに遺留分侵害額請求権を行使した場合、遺留分侵害者に対して遺留分相当額を請求することができる金銭債権が発生することになり、その金銭債権は通常の時効にかかります。
すなわち、「権利を行使できることを知った時」から5年間行使しない場合には、時効によって消滅します(民法第166条第1項第1号)。
以上のことから、遺留分侵害額請求には期間制限があるといえます。
遺留分侵害額請求権の時効を中断するには、どのような方法がありますか?
遺留分を侵害している相手方に対して、遺留分を請求する意思表示をする必要があります。
民法上、遺留分侵害額請求権の行使の方法は定められていませんので、同請求権は口頭で請求することも書面で請求することも可能です。
しかし、口頭で請求した場合、「言った・言わない」のトラブルが生じることが予想されます。
したがって、実務上は遺留分侵害額請求権を行使する場合、配達証明付き内容証明郵便で郵送することが一般的です。
参考リンク:郵便局・内容証明
このような方法で請求しておけば、請求時点が配達証明として残りますので、「言った・言わない」のトラブルを防止することができます。
代償分割に関するQ&A 相続税の税務調査についてもお願いできますか?